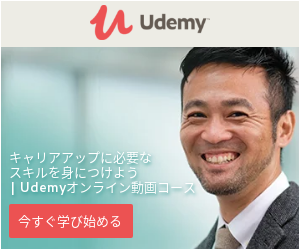PMI-ACPって何?
アジャイル方式のプロジェクトマネジメントの資格です。アジャイル実務のスキルを証明します。世界的に権威があるPMI(ProjectManagementInstitute)が実施する国際資格です。個人としては、スキル証明・人的ネットワークの拡大のメリットがあります。企業としては資格保持者がいると、案件への入札条件が満たされたりします。日本語あり。
非エンジニアでもいける?
この記事では、エンジニア経験(開発の現場経験)がない方でも、どのように対策を進めればよいかわかるように書いてあります。ただし開発用語は出てくるので、足りない場合は、紹介している書籍で補いながら対策を進めてください
※非エンジニアの方でも管理職で、取得を目指すニーズが一定数ある模様
受験の際には、アジャイル型の実務経験年数の要件を満たす必要がある。
1.直近3年以内でアジャイル実務を1500時間
2.直近5年間で2000時間のプロジェクトマネジメント実務経験
1は、厳密にアジャイル100%のプロジェクトである必要はない。つまり予測型のプロジェクトの中にアジャイルを混合したようなものでも構わない。アジャイルをうまく混合したという風に表現をすると要件を満たせる場合はおおいにある。まず要件を満たせるように、文章を考える必要がある。
また、PMP試験もアジャイル手法の割合が大きくなる(アジャイル:予測型=50%:50%)ように改訂された。(2021/3/1から)
PMP試験の前座としてアジャイルのことを知るために受験するニーズがある
筆者のスペック
2021年4月に受験して、1回目は落ちた。2回目で合格。
社内システム開発・プロジェクト管理の現場経験あり。システムを発注するビジネス側とそれを受ける開発側の両方の立場の経験あり。開発者としての経験があるので、試験によく出る開発系の用語には抵抗がなかった。
受験の動機
従来のプロジェクトマネジメント(=予測型)の知識で、私の頭の中は止まっていた。数年前にスクラムという用語を聞いてから本を読んだが、スクラム以外のアジャイルのことは知識が不足していた。知識の整理をしたいと思った時に、PMI-ACPの資格の存在を知った。
PMP試験(2021年から試験内容が改訂されて、予測型50%:アジャイル型50%になった)もいずれ受験するのでPMPの前座として受験を決意した。
参考書籍
Step1.スクラムのことだけ勉強する
スクラムと言われてピンとこない場合は、まずはスクラムのことだけ勉強することをおすすめします。
※必ずしも必要ないですが、私は知識の定着のためにスクラムの資格(EXIN Agile Scrum Foundation)も受験しました。
以下の記事を参考
非エンジニアでもいける? EXIN Agile Scrum Foundation 合格のための勉強方法
参考書籍を2冊読む
アジャイルサムライ
スクラムについて解説している。冗談も入っていておもしろい。
経験がない非ITの人の場合は、最初の一冊としておすすめします。とても読みやすくてわかりやすいからです。
IT用語が飛び交いますが、PMI-ACPの試験を受けるのであれば、この程度は辛抱しないと合格は厳しいでしょう。PMI-ACPはスクラムの理解が必須になりますが、もともとIT業界から始まったものだからです。本試験でも、IT用語の理解は必須です。
※今回の試験対策の中で、必須の本の一つ。読みやすいので、なるべく早めに読んでおきたい。
スクラム実践入門
スクラムについて解説している。スクラムの現場での事例・応用の事例がとてもわかりやすい。試験対策ではアジャイルサムライだけでは足りないので、この本のレベルがちょうどいい。
※今回の試験対策の中で、必須の本の一つ。アジャイルサムライの次に読むと理解が深まってちょうどよい。
Step2.受験資格を得る
PMIの試験を受けるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
・対象の講座を受講して終了証を発行すること
・PMIホームページにてアカウントを作成して、職歴や実務経験などの情報を記入して申込する。すべて英語です。1週間以内に、審査されて受領されて返信が来ます。遅すぎる場合は監査にひっかかっている可能性などあります。
今回、申込の要件や手順については他のサイトを参考にしました
※ここで申込後に運悪く監査の対象になると、職歴の記載事項などについて書面での提出などが必要になるらしい。今回は運よく、監査にはひっかかりませんでした。監査にひっかかる確率は10%以下と言われていますが定かではありません。
対象の講座について
21時間の公式の学習(アジャイル実務に関するプログラム対象の講座)が必須になります。好きなものを探して、自分で申込をします。
きちんと日本語の講座も用意されています。だいたい20000円くらいします。
私は英語の勉強もかねて、オンライン講座をUdemyから2000円程度で購入して修了しました。
おすすめの講座
全部英語です。キャンペーン中は2000円で買えます。Udemyはよくキャンペーンをしています。
8時間程度の充実したビデオ教材,理解度を測るためのミニクイズ,ミニ課題,小テスト,修了テストなど内容豊富です。
英語の音声は聞き取りやすく、文法も平易です。私の場合は、日本語の字幕を活用しました。
英語の字幕は標準で対応していますが、日本語で字幕表示したい方は以下のリンクで方法を参考にしてください。
以下参考
Udemyの英語教材を日本語で字幕表示して学習する
※講座を全部終わらせて、修了証を取得する必要あり。
修了の条件は、
・全ビデオの再生
・途中のワークの完了・ミニテストの完了
・最後のテストで及第点をとってクリアすること
テストは何度もやり直しがきくため、理解ができていなくても何度も受けていたら受かります。
英語はわからないので先に、日本語の教材であらかじめ勉強を行ってから、後で苦手な部分やテストの部分を日本語の字幕つきで実施する、という作戦もありだと思います。
あくまでテストに合格するだけならば、この教材は必須ではないと思いました。
それよりも他に紹介している日本語の教材を参考にしてください。
試験対策の方法
ECO(ExamContentsOnline)日本語版
無料。PMI-ACP試験の出題範囲として公開されている文書。公式ページからダウンロード可能。
しかしながら、日本語訳が怪しい。出題範囲の項目だけ羅列してあるため、事例に乏しい。これだけでは試験対策として足りないと思いました。
PMI-ACP試験パーフェクトマスター
日本語で書かれている試験対策の参考書。(2021/5/30現在で唯一)
ECOは必ず押さえておく必要があります。この書籍はECOに沿って、足りない部分が補足されています。今回の試験対策として、非常に重宝しました。
※余談ですが、英語の対策書籍ならたくさんあります。
公式で紹介している参考図書
アジャイル実務ガイド
PMI会員(有料)は無料でPDF版をダウンロード可能。ただし印刷はできないので、紙の本が読みたい人は購入する必要あり。
タイトルのごとく、アジャイル実務者向けに現場で適用できる内容。
アジャイルのエッセンスを実践レベルまで落とし込んだ具体的な内容が書いてある。
PMBOK(従来の予測型マネジメントのガイドブックのようなもの)との違いや対応関係をきちんと書いてある。そもそも、予測型のプロジェクトマネジメントと、アジャイル型のプロジェクトマネジメントは両極端である。それぞれを混合した方式も含めて説明している点はわかりやすいし、実務的にも役立つ。もちろん、試験対策としても役立つ。気になったのが、他の分野(教育・医療・研究開発など不確実な要素が大きい場面)でも活用できるということ。教育でどんなふうに活用するのだろう?とちょっと想像ができなかった。
※今回の試験対策の中で、必須の本である。なぜなら試験問題は、実際のケースに即して判断を問われる問題が80%程度である。この本は実例が書いてあるので参考になる。一方で、ECOはシラバス的に必須だが、具体的な事例がない。
※ただし、この本のすべてが出題されるわけではなく、あくまでECOの範囲内に限られる。隅々まで熟読しなくてもよいと思った。
※この本だけで対策が足りるわけではない。他の本も併読が必要だと思う。実務経験が豊富であれば補えるかもしれない。
カンバン仕事術
カンバンと言われてピンとこない人は、この本がおすすめ。カンバンの考え方は一度、イメージしないとわかりづらい。カンバンの問題はそれなりに出題されるので、試験対策にもなる。
ゴールドラット博士のボトルネック理論や、トヨタのかんばん方式は有名だが、話に出るだけで詳しい解説はない。ここでは開発の現場に生かすために考案された、"カンバン"(※かんばんが源流にある)という方式を紹介している。開発の文脈で語ってくれるので、開発者としてはとてもわかりやすい。スクラムとはだいぶ違う方式に見えるが、源流(無駄を省くためのリーン思考)は共通している。
例:チーム全体で一度に取り掛かる作業の数を減らして、リードタイムを短くする、など。
※今回の試験対策の中で、必須の本の一つ。なるべく早めに読んでおきたいおすすめの本。カンバンはよく登場するのだが、一見理解しづらいため。
アジャイルレトロスペクティブ
アジャイルを導入している組織の、日々の振り返り(=レトロスペクティブ)の方法論をたくさん書いている。実務的に使えそうな内容がわかりやすく書いてある。
※今回の試験対策では不要かもしれない。ここにあるアクティビティはECOにあるものよりも多い。試験対策はECOの内容だけ押さえておけばよいため。
アジャイルコーチング
アジャイルを導入することになった組織の、スクラムマスターやチームリーダー向けの本。コーチングも重視した内容になっている。あくまで、コーチングのための本ではなくて、アジャイルを導入する時の不足を補うための本である。
※今回の試験対策では不要かもしれない。読むならスクラムやカンバンが分かってから最後に読んだ方がよい。